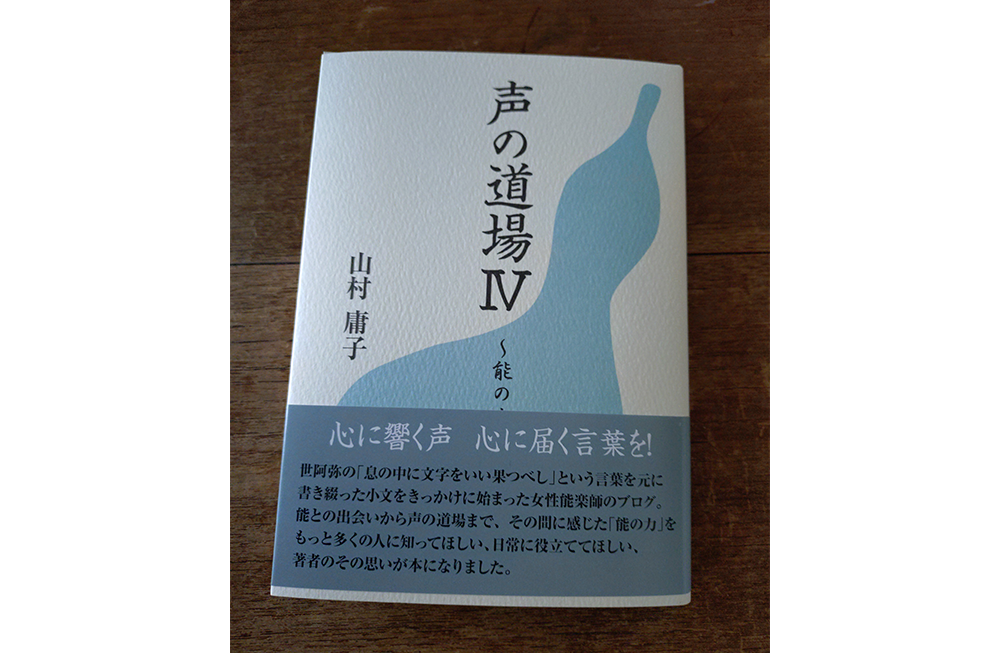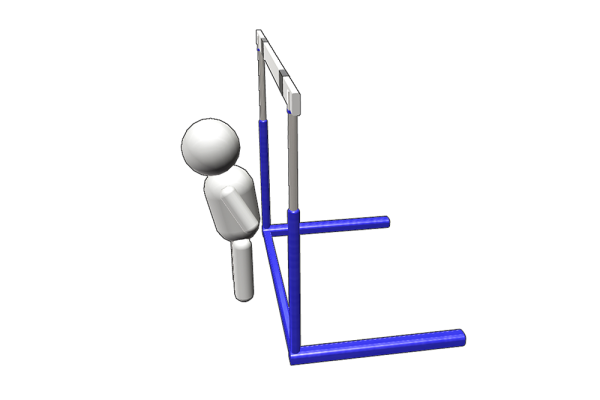「声の道場Ⅳ〜能の力を日常に〜」(一世出版)が発売開始になり、私の手元にも届きました。手に取ると、これまで出した三冊より頁数が1.5倍くらいあるので、ずっしり。持ち歩いて読んでいただくには少し重いかな、とは思いますが、編 […]
声の道場4冊目刊行のお知らせ
コロナの頃にお弟子さんが立ち上げてくださった緑桜会ホームページで、ブログを綴りだして5年、いつの間にか文章は相当な数になっていました。周りからのお勧めもあり、以前に発行させていただいた「声の道場」三冊の本に続き4冊目とし […]
ご報告
9月21日の梅若会定式能で「葛城 大和舞」を舞わせていただきました。足の状態が良かったり悪かったりで、どうなることかと思っておりましたが、どうにか無事に舞い終えました。とはいえまだ正座ができないので最初と最後は床几にかけ […]
舞台に立ちました!
昨年12月の定式能で富士太鼓の舞囃子を舞って以来、7ヶ月ぶりに舞台で仕舞を舞わせていただきました。もともと邯鄲を舞うことになっていたのですが、三月に靭帯を痛め、激しい動きや立居が難しいことから、曲目を変更していただき、舞 […]
やりすぎない
3月末に靭帯を痛めたあと、なかなか体が戻らないまま、杖にお世話になりつつ、少しずつ舞台や講座、稽古と復帰しつつあります。ただ、当たり前ですが元のようには行かず、何事もゆっくりなので動く時間は倍以上かかりますし、リハビリを […]
折って祈る
何年前からでしょう。何か心配事や気にかかることがあるたびに、気持ちを落ち着けるために小さな折り鶴を折っていました。何が起きたときも自分には祈るしかないな、と思ったからです。特にコロナが蔓延していた時には、終息を願って毎日 […]
またもや試練!
先日稽古帰りに夕飯の買物をしたあと、重い荷物を右手に持ち、バスに乗ろうと少し急いだ弾みに躓き、その瞬間に右膝に激痛が走りました。その前の週に2日続けて能の地謡に座らせて頂き、少し膝に安定感がなくて階段を降りるときに痛みが […]
「壁結」のこと
一昨年秋まで緑桜会を催していた、福岡県うきは市にある私の実家、楠森堂には、300年来続いてきた「壁結」という伝統行事があります。屋敷の周りに150mほどの竹垣があるのですが、毎年三月頃古くなった内側の竹を四分の一ほど取り […]
舞納めと舞初め
12月15日今年最後の梅若会定式能で、舞囃子「富士太鼓」を舞わせていただきました。今年の舞納めです。二日前の申し合わせの日は何ともなかったのに、その夜から鼻風邪をひいたのか、クシャミや咳が出て夜は眠られず、定式当日まで咳 […]
「繋の会」が終わりました
第一回「繋の会」が無事終了しました。 一部の緑桜会会員の発表会は、いろいろ楽屋でハプニングはあったものの、皆さん動ずることなくしっかり演じられました。観にいらした方から「長年なさったお上手な方はもちろんですが、まだ始めた […]