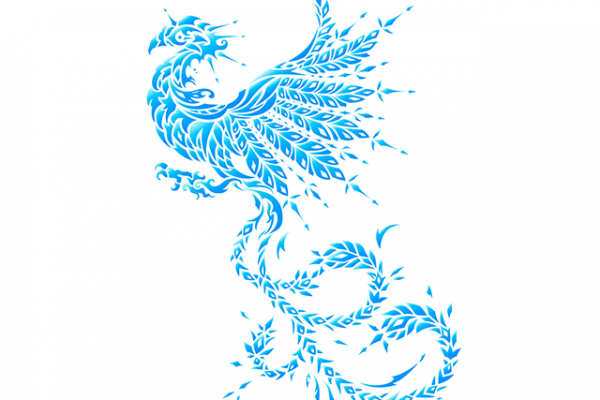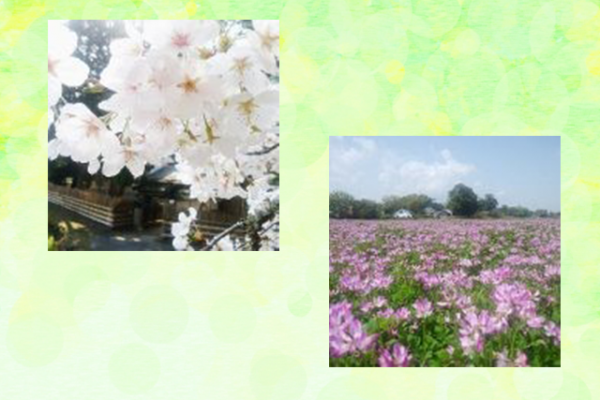一昨年秋まで緑桜会を催していた、福岡県うきは市にある私の実家、楠森堂には、300年来続いてきた「壁結」という伝統行事があります。
屋敷の周りに150mほどの竹垣があるのですが、毎年三月頃古くなった内側の竹を四分の一ほど取り外し、前年の秋に山から切り出して準備しておいた竹を、外側に加えて結い直すのです。
山から竹を切り出すのも、竹を火であぶって角の形を作るのも、もちろん壁を結い直すのも、とても力と技術がいり、多くの人手が必要です。
昔から地域の方たちとのいい関係の中で、毎年多くの人に手伝っていただいていました。お昼や作業後には、用意された食事を一緒に飲んだり食べたりおしゃべりしたりして1日を楽しむ、という祭事のような行事だったように思います。
他の行事もそうですが、現代のように旅行や遊びが簡単にできなかった時代、地域の皆で楽しめるレクレーションのような役割もあったのかもしれません。
小さい頃、広い土間の台所で皆に振る舞われる大量の団子汁を作っている様子や、だんだんに竹壁が出来ていく様子をワクワクしながら見ていた記憶があります。
戦争の頃など一時期途絶えることもあったとは思いますが、「壁結」はそうやって長年続いてきた、地域の人たちとの繋がりを深める大事な行事でした。
時代が変わり、地域との繋がりも薄くなり、若い人が減り、昔のように大人数で「壁結」ができなくなっても、楠森堂を守ってくれている兄と甥はどうにかして続けようと努力してきました。
そのうち兄も手伝ってくださっていた同世代の方たちもだんだん年を取って無理ができなくなってきました。そこで甥は新たに自分の周りの人たちとの繋がりを深め、また「壁結」という伝統行事があることをSNSで周りに発信していきました。
その甲斐もあってか、テレビのドキュメンタリーやニュース、新聞にも取り上げてもらうようになり、少しは「壁結」のことを皆さんに知っていただけるようになったのです。
そこで甥は「壁結」当日のボランティアを募集することを始めました。興味のある方がたくさん応募してくださり、そのお陰でどうにか「壁結」という行事を続けられたのでした。
経験のない方たちに、最初からお教えするところから始めるのはとても大変だったと思います。
甥はそうやって苦労しながら何年かはどうにか行事を続けてくれていました。ただ前年からの竹の用意が大変なのに、そのための人集めはなかなか思うようにはいかなかったようです。また毎回同じ方が来てくださるわけではなく、毎年人が集まるかどうか綱渡りのような形だったと思います。
またその後コロナの流行もあって「壁結」の行事の継続はいよいよ難しくなり、ここ何年かは朽ちていく竹を結い直すのが精一杯だったといいます。台風のたびに薄くなった壁が倒れ、それを直すのも大変のようでした。私も「これまでよく頑張ってくれたけれど、今の時代にこういう行事を個人で続けるのはそろそろ無理かも」と思い始めていました。
ところが昨年、甥の努力と気持ちが周りに通じたのか、
「この伝統行事を残そう」
と、うきは市役所の文化財保護係の方が動いてくださり、応援のお声がけをいただきました。そして6年ぶりに今年の3月8日に「壁結」ができる運びになったたのです。今年できなかったらもう続けられない、という時に、嬉しい驚きのニュースでした。
当日の作業以前に前年の秋からの準備がとても大変なのですが、昨年秋の竹の切り出しから、竹を火で炙って形を整えたり、切りそろえたりする作業まで市の職員の方々のお手伝いをいただきました。一ヶ月以上に及ぶこれらの作業で、6年間で朽ちた竹を補充するために必要な、いつもの何倍もの量の竹を用意することができ、「壁結」のための7~8割方の準備作業ができたそうです。
当日はこのような伝統行事に興味のあるボランティアの方も募集しています。前の時と違い、中心になってくださる方が甥の周りにいらっしゃるのがとても心強く、多くの方に「壁結」を経験していただければ嬉しいなと思っています。
途切れそうになった300年続いてきた行事が息を吹き返す、繋いで行くことができる、ということが本当にありがたく、声をかけてくださり、お力添えをしてくださった方たちに感謝の気持で一杯です。私は直接手伝うことはもう叶いませんが、無事に「壁結」の行事ができることを心から祈っています。
能楽師としての私は、昨年から「繋の会」という「先へ繋ぐ」ことを目標とした会を始めました。
楠森堂での会は一昨年で終わってしまいましたが、形を変え気持ちを繋いでいます。時を同じくして実家で伝統行事を繋ぐ再スタートが始まることをとても嬉しく思っています。
興味のある方は是非「楠森堂ブログ」で検索なさってみてください。
「古き良きもの」を残そうと奮闘している様を知っていただけたら嬉しいです。