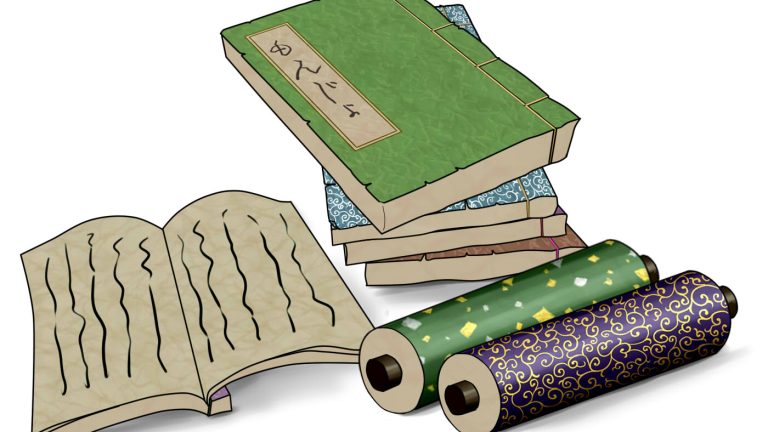何日か前、偶然昔の伝書を研究している方のサイトの中に、豊臣秀吉や徳川家康に目をかけられていた金春流の大夫、金春安照(1549〜1621)の文章を見つけました。
うたいハ はらにほねおらせ候へば かほにクセなき物也。うたいにも 云ひ出す文字 云ひはなす文字 大事也。心がけ専也。うたいはつる文字 云いだす文字と同前也。うたい出した文字を云いはつるまで忘れず候 と申し伝え候。
現代語に訳すと
謡は腹に力を込めれば無理をした顔にならないですむものである。謡い始めの言葉と謡い終わりの言葉は、特に大事であるから注意が必要である。終わりのところの謡は謡い始めと同じようででなければならず、始めの箇所を謡い終わるまで心に留めておかねばならない ということを伝えたい。
また、その他にも謡を口内芸術と言っていて、発声や発音などを意識した稽古が大事、と伝えている。心が自然に表現される謡が一番だと。感情を表に出し、声でいろいろ作って表現しようとするのはよくないとも。
自然に発せられる言葉を、腹の力で溜まっている息の中に言い放つことにより、自然な感情が表現されるということを言っているのだと思います。
私はお教えする時、息に声を乗せるための説明に
「謡い始めの文字で体の中に息のパッケージを作り、おなかの力を維持したまま最後の文字まで謡い切る」
という言い方をしていましたが、同じ感覚のような気がして嬉しくなりました。
450年ほど前の名人と言われた能役者、金春安照の言葉です。
600年以上前の世阿弥の伝書にある
「息の中に文字を言い果つべし」
「唯声を彩り曲をなさんは音曲正路にはあるまじきなり」とも同じ感覚だと思います。
このように昔から、能役者によって発声については研究努力がされてきたのです。
能は外で演じられ、面を着けマイクもなしという中での必然の努力だったことでしょう。
能楽堂で舞うことが多く、野外ではマイクが使われるようになった現代、能楽師によるその努力はどのくらいなされているのかな、と思います。面をつけることによって、ある程度は腹を使うので、他の舞台演劇に比べると声が強いということに安住し、全体としては何となく緩んできているのではないのかな、と感じることもあります。
もちろん、この方は若い頃から研究されてきたのだろうな、というすごい方もいらっしゃいます。ただ、これから能役者として育つ方にはもっともっと自分の体の内なる研究をしていただけると嬉しいなと思うこの頃です。