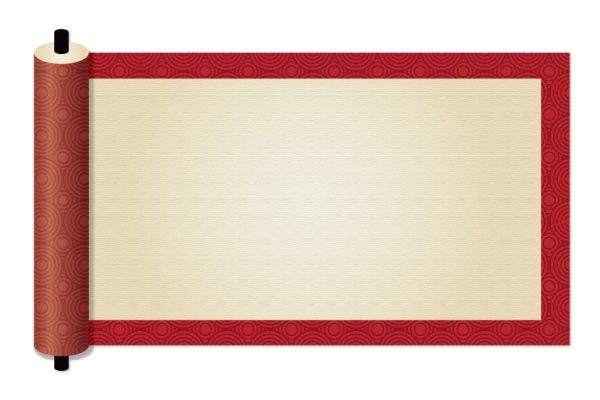能楽師になって初めの頃、小学校に通っている娘が言いました。「ママ、学校の友達みんな能って何か知らないんだよ」子供たちは私の舞台を観に来たこともあり、私の実家には敷舞台があり、扇や写真もたくさんあったので、みんなが能を知ら […]
危機を節目に 3
40代半ばと50代半ばに「能が舞えなくなるかも」と思うような出来事があり、それを乗り越え良い節目になったことをブログの中で前に述べました。今回のお正月転倒事故は私にとってその2回に次ぐ危機でした。 まだ腰に違和感が残ると […]
危機を節目に 2
50代半ば、14.5年ぶりで主人とボウリングに行ったときのことです。学生時代ボウリングクラブに所属していて、全国大会にも出場していた私は、昔通りのイメージでゲームをしました。思ったよりスムーズに投げることができ、得点は1 […]
ダブル鬘?
前回の「危機を節目に」で述べた、46歳のときに脳動脈瘤をクリップで留める手術を受けてすぐの頃の話です。 退院して2週間あまり…髪の毛を全部剃っての手術でしたからまだ1センチぐらいしか髪が伸びていなくて、外出時は鬘を付けて […]
危機を節目に!
40歳で能楽師になって34年になります。その中で「もう能ができないかもしれない」と思ったことが三度ありました。 最初は46歳のときでした。猛暑の夏、突如経験したことのないような頭痛に襲われました。冷やしても薬を飲んでも治 […]
命の恩人の鞄
20年ほど前、一度だけヨーロッパ公演のお手伝いに同行させていただいたことがあります。その折アムステルダムで連れて行っていただいたお店で、ある先生に「袴を入れるのにとても使いやすい」と教えていただいた製図鞄を買いました。軽 […]
新しい目標
昨年末の「女流能に親しむ会」で舞った舞囃子「山姥」は私に新たな目標を作ってくれました。若い頃からの課題曲でありながら、師匠の素晴らしい能を何度も拝見し大好きな曲でありながら、仕舞では何度か舞いましたが、能として取り組むこ […]
師の教えから
平成8年に福岡で初めて自分の能の会を立ち上げさせていただいて、その二年後東京の梅若能楽学院で二回目の会のときに、まだまだ私には難しい「隅田川」をお許し頂きました。必死でお稽古した上で、師匠にも二度(いつもは一度)見ていた […]
厳しさと温かさと
11月17日、高安流大鼓方の人間国宝、柿原崇志先生がお亡くなりになりました。お電話でご訃報を伺ったときは、しばらくボーッとしてしまいました。そして次から次から先生との思い出が浮かんできました。懐かしく、そして寂しく悲しく […]
父の仕舞
父が仕舞をいつ稽古し始めたのかよく覚えていませんが、父の舞台を観るようになったのは、私が大学を卒業してからなので、父はもう60代半ばになっていました。娘の目から見てもなかなか風格があって、素人としては上手だったのではない […]