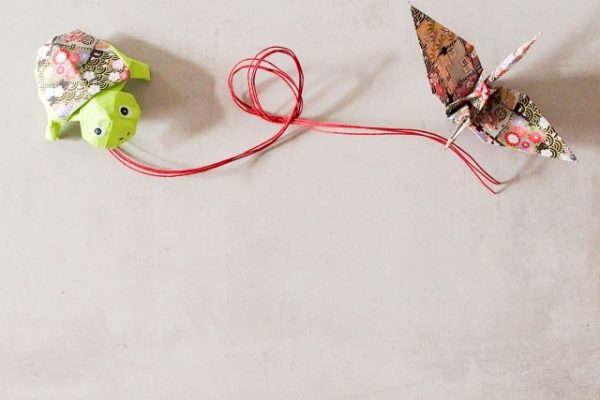前回「柱が作る三間四方」という題で、能舞台のことを書きましたが、その舞台の広がりに無くてはならない「橋掛かり」について述べたいと思います。
「橋掛かり」は揚幕から舞台まで、能楽堂によって多少の違いはあれ、ほぼ丁度いい長さは決まっているようなものですが、その距離感は「縦横無尽」その役割は「変幻自在」だと私は思っています。
現在能(今現在の時間の流れでドラマが進展していく能)では、遠い所からの旅を表す時間軸になっていることもあり、また近い所では、揚幕やシテ柱の位置で外と内を分ける玄関となることもあります。
夢幻能(前場にシテは化身として現れ、後には当時の姿で昔を語り消えていく…ワキの夢の中のように思える能)ではあの世とこの世を繋ぐ、次元を変える役割もしています。舞台は今現在のこの世。揚幕の向こう側はあの世。あの世からこの世に掛かる橋を渡り、現実の世界である舞台に亡霊が現れるのです。橋掛かりは「どこからともなく」という場面を作るのです。
橋掛かりの舞台への角度も登場退場の効果に絶妙です。また、揚幕からシテ柱までにある二本の柱の間に設置される3本の松は舞台から順に一ノ松ニノ松三ノ松と名付けられていますが、少しずつ小さくなり、幕を出て舞台へ到るまでの遠近感がより感じられるようになっています。
「橋掛かり」の距離感には横の軸だけでなく、縦の軸もあります。神が降臨したり、天人や菩薩が空に消えていったり、また龍神が水底から出現するという場面にも効果があります。
このように「橋掛かり」は曲によってお客様が謡を聞きながらイメージを広げられるのに重要な役割を持っています。
その能の場面の設定は、語られる言葉によってお客様が想像なさることによって、舞台が変わるのですが、その舞台が都であったり、名所旧跡であったり、海であったり山であったり様々です。それによって、またその展開によって、橋掛かりもいろんな役割を果たしていく、ということなのです。
私が「橋掛かり」のことを、距離感「縦横無尽」、役割「変幻自在」と言う所以です。

揚幕から現れる写真は、夢幻能「東北」の前シテ和泉式部の化身で、ワキの旅僧に呼びかけて会話をしながらどこからともなく現れるところです。舞台は都「東北院」、そこに咲く「軒端の梅」と和泉式部のことを語り……花の陰に木隠れて失せにけり木隠れて見えずなりにけり……と舞台で終わり静かに橋掛かりから幕へ消えていきます。
後シテは和泉式部の姿で現れ昔を語り舞い……方丈の室にいると見えし夢は覚めにけり見し夢は覚めて失せにけり……とこれも舞台で終わります。前も後も謡や型は舞台で終わるのですが、橋掛かりのアユミは何処ともなく消えていく余韻となるのです(そうならなければいけないのですが…)。

揚幕に入る写真は、現在能「班女」の後シテ花子です。美濃の野上の宿の遊女花子は、都から東国へ向かう途中宿に立ち寄った吉田の少将と恋に落ちます。互いの扇を取り交わしてまた逢う約束を交わした花子が、扇ばかりに気を取られ働かないのに業を煮やした女主人は花子を追い出してしまいます。その時は舞台は野上の宿、ボーッと気が抜けたように足を運び、橋掛かりは何処ともなく花子を誘います。
後では花子は物狂いとなって橋掛かりに現れます。扇を懐き少将を恋い慕い、神々に再会を祈願しつつ都にたどり着くまでの日々が橋掛かりにはあるのです。吉田の少将も花子とのすれ違いに気を落とし都に戻りますが、ある日糺へ参拝に訪れたとき(舞台は今度は糺の森となっています)そこで扇に想いを込めて狂い舞う女に出会い、花子と気付き互いに扇を見せあって喜び合う、というハッビーエンドなのですが……扇のつまの形見こそ妹背の仲の情けなれ……と舞台で終わって共に帰っていくという、橋掛かりは現在進行形の道筋となります。
いつも、このあと「二人はどうなるのかな?」と思ってしまうのですが、それもお客様の自由なイメージに託す、能特有の終わり方であり、橋掛かりのシテのアユミがその後をイメージする余韻となるのではないかと思っています。