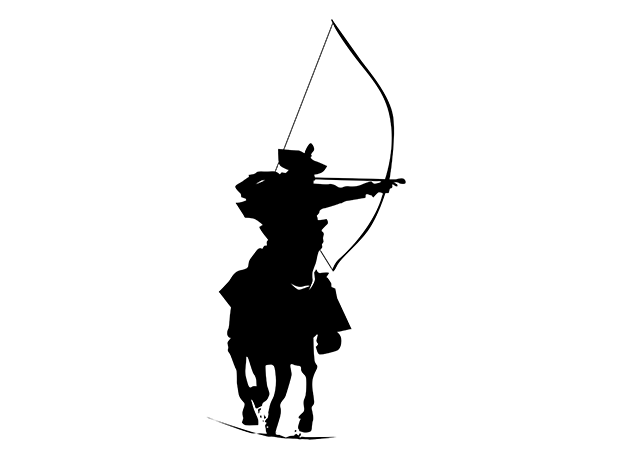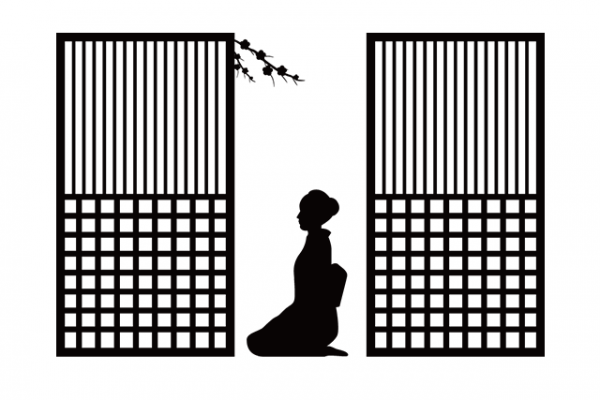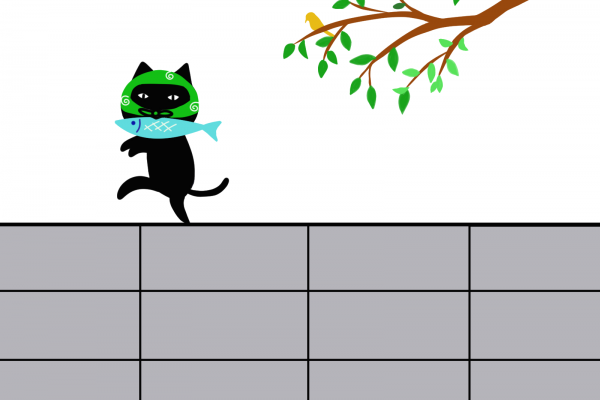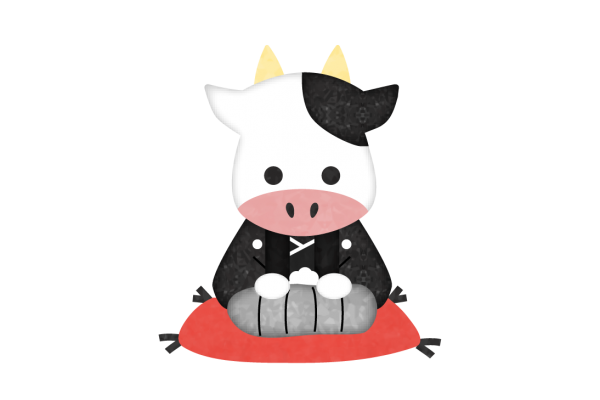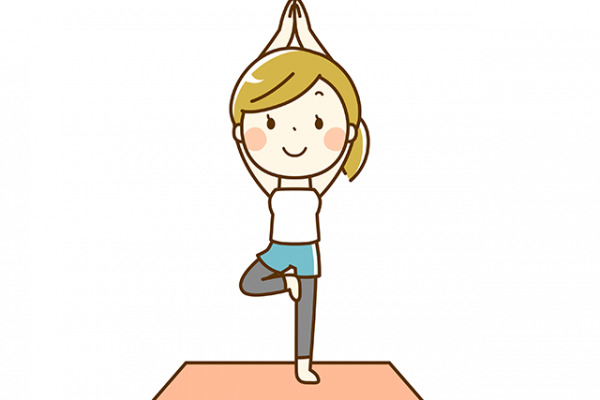日本の文化や習慣に興味があり、「どうしても日本に行きたい!」という願いを持つ外国人を日本に招待するテレビ番組があります。ある回で「流鏑馬」を身に着けたくて、自分で研究している、というフランス人男性が日本に招待されていまし […]
肩で風を切る
私は能エクササイズで、「和の構え」をお教えするのに「上半身を動かさない」ということをいつも言っています。 テレビを見ていても画面に出てくる人の姿勢のことが気になるのですが、いわゆる「姿勢が悪い」という人以上に、胸を張り肩 […]
君が代と民が世
声の道場のワークショップで、受講生に和の発声を体験していただくときは、まず和の構えをお教えして、その後ハミングや母音を体に響かす練習をします。次に息に子音を乗せる稽古、言葉を乗せる稽古を繰り返します。そのあとで皆さんご存 […]
能のデッサン
「仕舞は能のデッサン」とよく言われます。私も「能と日本画」で能と絵画の繋がりを取り上げていますが、絵画において、まず形を的確に捉えるデッサンの修練は、能においてはその芯を形造る仕舞の稽古に当たると思います。 若い頃、いろ […]
「見る」と「見える」
銀行に行って、ATMが混んで並んでいるとき、その台数が多く横に長いと次に空いたところに気づかず、係の人から教えてもらうことがあります。それで特に困るわけではないのですが、この頃私はどうしたら自分ですぐに空いた場所がわかる […]
抜き足、差し足、忍び足
-能エクササイズ実践 2- 「和の構え」に続き、2回目は「すり足」の稽古に入る前に、片足にしっかり重心を乗せることを体感するための稽古からです。「片足立ちの効用」の回でも述べましたが、この稽古だけでも十分健康維持に役立つ […]
和の構え
-能エクササイズ実践 1- 能において「すり足」は基本中の基本です(すり足とずり足参照)。仕舞のときももちろんお教えするのですが、どうしても型や順序に気を取られ、おざなりになってしまいます。そこで仕舞に関係なく健康のため […]
わからなさを面白がる
朝日新聞の朝刊に、毎日「折々のことば」というエッセイがあります。時々私のアンテナにピッと来るものがあるのですが、ある時「わからなさを面白がる」という文に目が止まりました。 玄田有史さんの「希望のつくり方」という本からの言 […]
体をイメージする
ヨガなどで「○○のポーズ」などといって、自分の体を何かにイメージしていろんなポーズを取ることで、体を整えることがあります。私も一度だけ体験させていただいたのですが、横たわったり座ったりしてのポーズは思ったよりできました。 […]
ハミングでのチューニング
ハミングといえば、軽く鼻に響かせるものと誰もが思っています。けれども「声の道場」では、ハミングを使って「体が楽器」だということをお教えしています。この稽古法は私にとっても驚きの発見でした。 「声の道場 3」にも詳細は書い […]