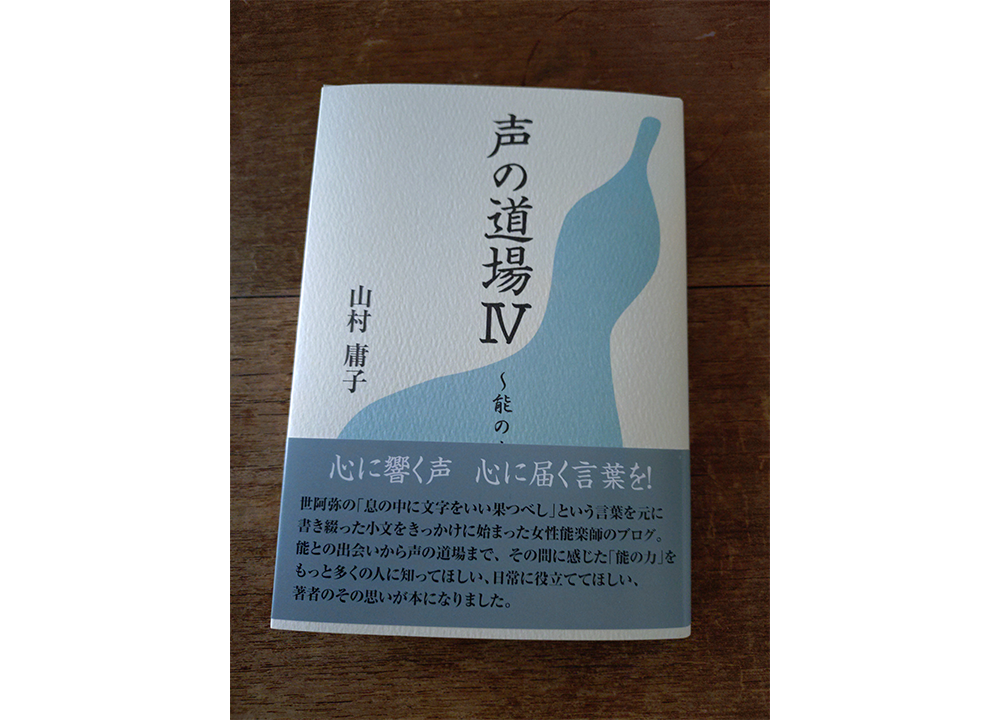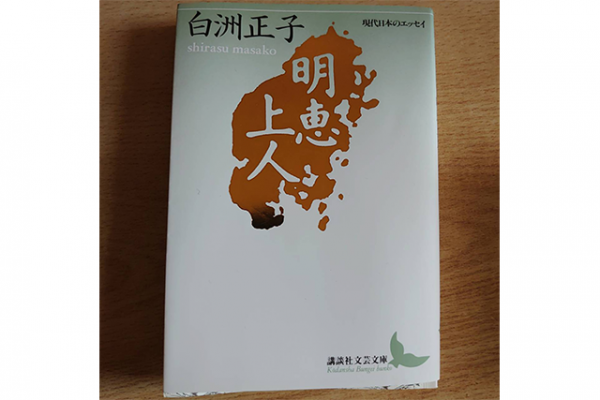私は今から14年前に、和の発声を体験していただくために、謡の稽古とは別に「声の道場」を始めました。そして2年前、今度は健康のために仕舞の稽古とは別に、能の体の使い方を体験していただく「能エクササイズ」を始めました。 能が […]
楠森堂
毎年この時期は、福岡県うきは市にある、私の実家「楠森堂」で緑桜会の催しをするための準備に忙しくしていました。今年はコロナが収まらないこともあり、残念ながら中止に・・・。なんだか忘れ物をしたような気分です。 私の先祖は古く […]
来年が動き出しました
昨年末から今年2月にかけて、新宿朝日カルチャーセンターからの依頼で、何度か「声の道場」の講座をさせていただきました。おかげさまで多くの方が参加してくださり、また次回 もというお話をいただいたところで、緊急事態宣言!カルチ […]
あるべきやうわ
40歳で観世流シテ方の師範に推挙していただいたとき、上の娘は小学校2年生、下の娘が幼稚園年長でした。そのため能楽師とは言っても名ばかり、出勤は最小限。毎月の定式能とその申し合わせだけにさせていただき、その他は師匠のお弟子 […]
サントリーホール
師匠(梅若 実師)の作られた新作能は数多くありますが、中でも「空海」は幾度となく再演され、好評を博しています。能楽堂以外の海外や国内のホールでの上演も多く、初演当時は時々楽屋の手伝いに伺わせていただいていました。 初めて […]
梅若会トライアル公演
10/18の第一回のトライアル公演、お陰様で無事に終了いたしました。 いらしてくださった皆様ありがとうございました。 続いて11/7㈯には「晩秋の調べ」が催され「音」「光」「香」と共に仕舞と素謡を楽しんで頂く企画となって […]
玄人としての初シテ
40歳の時に玄人に取り立てていただき、能を舞わせていただくことなどまだまだ先のことだと思っていたのに、2年目の平成2年、靖国神社の大祭での奉納の能で初シテをさせていただくことになりました。毎年恒例の奉納の能は、当時書生さ […]
初めての能
私が初めて面を付けて能を舞わせていただいたのは28歳のときでした。本当は父が70歳の古稀のお祝いに舞うはずだったのですが、糖尿病がひどくなり立ち居がままならなくなったため、代わりに私に舞うようにということになったのです。 […]
お転婆娘
仕舞が面白くなったきっかけはチャンバラでした。扇を刀にして斬ったり刺したり飛んだり・・・。女でも関係ありません。それが快感だったのです。 私は子どもの頃から兄三人の影響を受け、野球や相撲が大好きで、やることなすこととても […]
笛の息と謡の息
「謡は腹の力で体に溜めた息を遣って謡うものだ」と頭でわかってきたとき、いい稽古方法を思いつきました。 能の笛が大好きで田中一次先生に憧れ、必死で真似していた頃です。笛も体に溜めた息を歌口に当てて音を出し、その当て方によっ […]