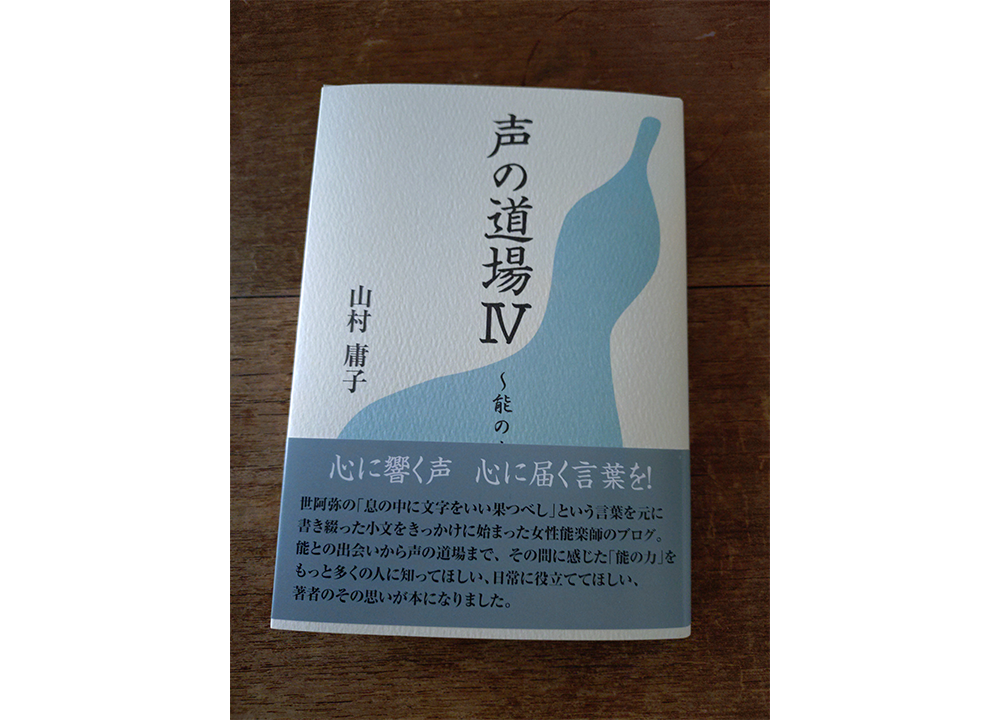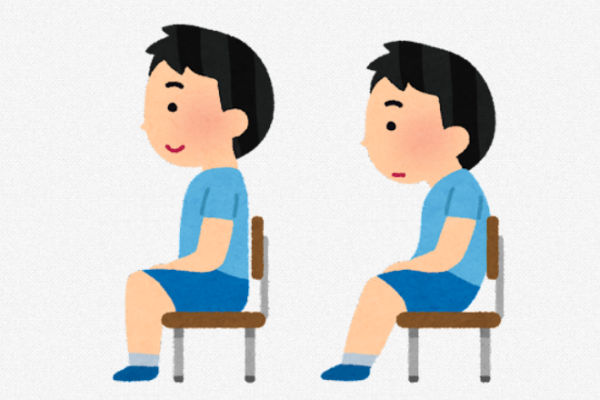今年の元旦のブログで自分のやるべき目標を新しく掲げました。やりたいこともたくさんあり、動き出したところでもありました。ところがそれから一週間も立たぬうち、2022は思いもよらぬアイスバーンでの転倒事故に始まってしまいまし […]
楽しい背くらべ
家の近くに住んでいた娘が11月初旬、少し離れたところに引っ越しました。日帰りができない距離ではないのですが、なにか用があるとすぐに会えたときと比べると、そうそう行けない距離です。先日、14歳になる孫娘の誕生日ということで […]
違いが歴然
前に子供たちに本物の能狂言を見せるための巡回公演の一環で「小学生の謡体験」を受け持たせていただいたことを書きましたが、今度は中学生相手に謡体験をしてもらう機会をいただきました。能の前に限られた時間の中で10分ほど、人数は […]
会の後の楽しみ
先日の楠森堂の会が終わった後、東京に帰るまでの楽しい話。 東京から参加のグループは、会が終わるといつも筑後川温泉に泊まることにしています。今回はコロナということもあり、あまり大勢一緒でない方がいいと考え相談して、もうひと […]
楠森堂の空気感
11月26日(土)、楠森堂での緑桜会が無事に終了しました。私達が滞在した25,26,27日、真っ青に晴れ渡り、コートもいらないような暖かい3日間でした。楠森堂の古い家は外が暖かくても中に入ると冷気があるのでいつもお客様に […]
反復稽古の成果
梅若会素謡会が終わりました。正式な会での独吟は初めてで、ほんの七八分なのですが、能や舞囃子に比べるとまた別の緊張感がありました。他の出演者も同じで、楽屋も独特の雰囲気でした。終わった人の緊張感が溶けていく中、最後の方だっ […]
狂言とサザエさん
私が最初に太鼓をお習いした津田美代子先生は福岡の女学校時代、漫画家の長谷川町子さんと同級生でいらしたそうです。今でもテレビで放送されていて誰でも知っている「サザエさん」はじめ「意地悪ばあさん」「弥次喜多道中」など、長谷川 […]
小学生の謡体験
先日、地方の小学校で能を体験してもらう催しに参加させていただきました。短い狂言と能の一部分を鑑賞してもらうのですが、その解説と囃子のデモンストレーションの進行、子どもたちの謡の体験を受け持たせていただきました。一年生から […]
楠森堂で緑桜会
令和元年まで七年間続けて福岡県うきは市の私の実家「楠森堂」で開催しておりました「秋の緑桜会」ですが、コロナの感染が収まらず二年間開催できませんでした。まだまだ収束とはいきませんが、今年は出演してくださる方々とご相談の結果 […]
「笠ノ段」を謡う
11月20日(日)の梅若素謡会で、「笠ノ段」を謡わせていただきます。梅若会で独吟をさせていただくのは、能楽師になって初めてのような気がします。「笠ノ段」は能「蘆刈」の中の、よく知られた謡いどころ舞いどころで、私もとても好 […]